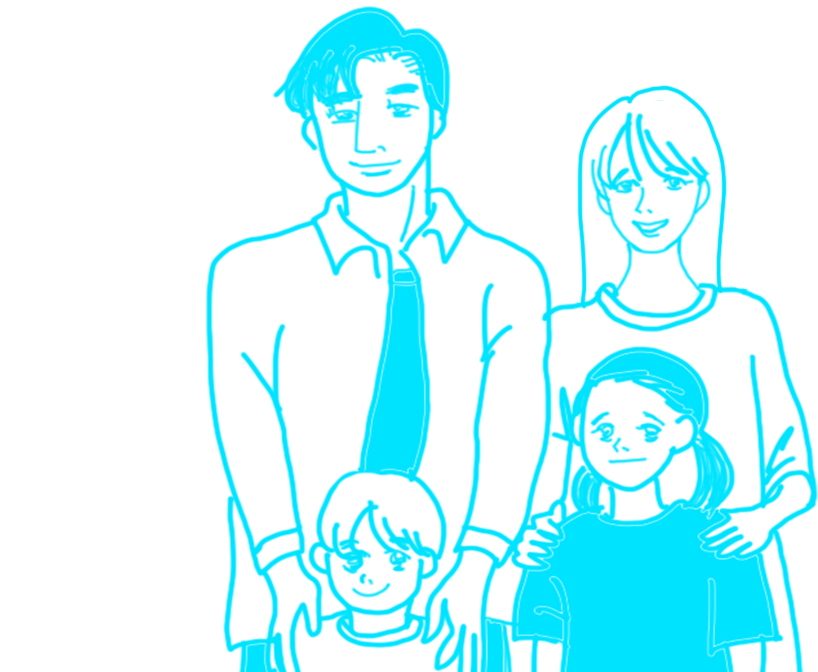
今回の登場人物
相田はるか(10)
小学校4年生。
両親の影響で自然が大好きな、心優しい女の子。
悠(6)
はるかの弟。明るくて元気な男の子。
保育園の年長。来年1年生になる。
お父さん(40)
京都のデジタルマーケティング企業で働いている。
キャンプが好き。
お母さん(39)
フリーランスのデザイナー。
娘の気持ちをとても大事にしている。涙もろい。
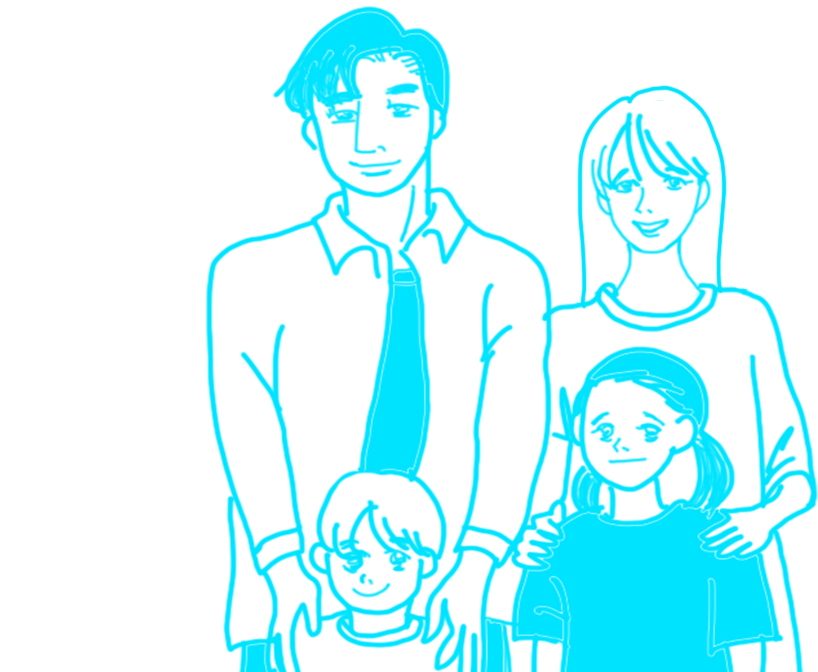
今回の登場人物
相田はるか(10)
小学校4年生。
両親の影響で自然が大好きな、心優しい女の子。
悠(6)
はるかの弟。明るくて元気な男の子。
保育園の年長。来年1年生になる。
お父さん(40)
京都のデジタルマーケティング企業で働いている。
キャンプが好き。
お母さん(39)
フリーランスのデザイナー。
娘の気持ちをとても大事にしている。涙もろい。
小学4年生になったはるかは、新しいクラスに馴染めず、
学校へ行くことがしんどく感じている今日この頃。
そんな娘の様子を見ていた父は心配になり、長男の進学を機に環境を変えることを検討。
職場でリモート勤務が可能になったので、
自然に近い場所に引っ越そうと決意を固める─────
今日も、ぜんぜん学校に行きたくない。
朝起きてすぐなのに、学校に行く準備をしていると、体がどっと重たくなる。
いややなぁ。行きたくないなぁ。
でもお母さんが心配するから、ちゃんと行かなくちゃいけない。
トースターで焼いたパンに、いちごのジャムをぬる。
朝ごはんは最近、ごはんからパンになった。前までは、甘いジャムとパンは休みの日だけだったのに。わたしがぜんぜん食べないから、お母さんが「食べないよりはまし」と折れたのだ。食欲はないけれど、やっぱりお母さんが心配するから、ちゃんと食べる。
弟の悠が、ジャムをすくうスプーンをなめてしまった。
「だめやで、それまだ使うんやから」
わたしは仕方なく、代わりのスプーンを取りに行く。
悠と一緒に保育園に行けたらどんなにいいだろう。「あのころはよかった」なんて言ったら、笑われるだろうか。
私はもう小学4年生なんだから。
お母さんが「もうそろそろ時間やで」と言う。やさしく、なんでもないように。

4年生になってから、学校が楽しくなくなった。
3年生までもそんなに楽しいわけじゃなかったけれど、それでも今よりましだった。
男女関係なく話すことができたし、休み時間に誰が何をしても、誰も気にしなかったし。
いい意味で、お互いに興味がなかったんだと思う。
だけどだんだん、誰かが誰かを好きになったり、きらいになったり、見た目を気にするようになっていった。
恋バナとか、悪口とか、服や筆箱や髪型がどうのとか。
わたしは、周りの話題にぜんぜんついていけなかった。
春になってクラスが変わってから、みんなあっという間にグループをつくったけれど、わたしはどこにも入れなかった。
初めて同じクラスになった吉永さんが、わたしのことをきらっているようなのだ。
なんでなのかはわからない。でも、きらわれていることはわかる。
よくわたしの方を見てこそこそ話をしているし、くすくす笑いをしているし。
吉永さんは明るくて目立つ子だから、彼女のふるまいはすぐ新しいクラスに行きわたった。
教室に入ると、心なしかみんながしんとする。
だから、わたしはいつもチャイムギリギリになるよう、ゆっくりゆっくり歩いて行く。

今日は少し早く着いてしまいそうだったので、裏庭で時間をつぶすことにした。
裏庭にはだれもいなくて、ほっとした。木のまわりにハルジオンが咲いていて、わたしはそれをしゃがんで眺める。
前に、植物が好きなお父さんが教えてくれたのだ。「ハルジオンは、どこにでも咲くんやで」と。
「お父さん家には植物を育てるような庭がなかったんやけど、玄関先に咲いてくれて嬉しかったなぁ」
そんなことを思い出していたら、足元にサッカーボールがころがってきて、誰かがそれを追いかけてきた。
「おお、相田さん。何してるん?」
それは、3年生まで同じクラスだった森川くんだった。
わたしはとっさにうまい理由を思いつけなくて、「ええと、ぼーっとしてた」と答えた。
すると森川くんは「なんやそれ」と笑ったが、わたしの顔を見て急に心配そうになり、「どっか痛いんか?」と聞いてきた。わたしが涙目になっているのに気がついたのだろう。
「目にゴミが入って……」
下手なウソをついた時、「森川ー!」と運動場から声が聴こえた。
わたしは「そろそろ行かな」と言い、走ってそこから逃げた。
それからだ。わたしが森川くんに告白したといううわさが流れ始めたのは。
吉永さんは泣いていた。わたしはいろんな子に「ひどい」と言われたり、からかわれたりした。
本当に、わけがわからない。

「ごめん、もう学校行けへん」
ある日の夕食後、わたしはお母さんとお父さんに言った。
行きたくない、ではない。行けないのだ。
できる限りがんばったけれど、もうこれ以上は無理だってことがわかる。
二人は「どうしたん?」「何かあったん?」と聞いてきた。何度もこれまでに聞かれたことだ。
でも、わたしは何も答えられなかった。理由なんてあるようでない。ただ、あそこになじめないだけだ。
悠も心配そうに「はるか、どうしたん?」と聞いてくる。
わたしは泣いていた。なんだか情けなくて。
なんできらわれるのか、なんで「ひどい」と言われるのか、わからないからどうしようもない。
「わかった、もう行かんでいいよ」
お母さんがそう言った。「うん、行かんでいい」とお父さんも言う。
「ほんまに?」
「ほんまに」
二人が声をそろえて言った。わたしはほっとして、もっと涙が出た。お母さんがちょっと泣いているのがわかった。
お父さんが、
「じゃあ明日、お父さんに付き合ってくれへんか」
と言った。
「はるかと一緒に行きたいとこあんねん」
涙をふきながら「どこ行くん?」と尋ねる。すると悠が「ぼくも行くー!」と大きな声で言った。
「膳所ってところ」
「ぜぜ?」
「うん。滋賀の大津に、そういうところがあんねん。悠は危ないから、また今度一緒に行こな」
駄々をこねる悠を、お母さんが抱っこしてなだめる。
「明日、二人で行っておいで」
お母さんも、ほっとしたように笑っていた。
そんな顔を見るのは久しぶりだった。
【文章】土門蘭